
それぞれの段と行を指示する記号として、アルファベットを借用する。a行のみは、段を指示する座標軸であるとともに、それ自身文字であるという二重の性格を持っている。a行は正しくは「ゼロ行」なのであるが、慣用にしたがって「a行」とする。われわれの立場は、西洋語の音素による日本語の解析ではない。あくまで座標の記号として用いる。
定義集で定義するのは、現代日本語である。とりわけ、現代日本語における構造語である。ただし、重要な言葉については、古典日本語もとりあげる。
見出し語はかなで表す。同音別語は区別のために( )内に漢字を一つつける。また「辞」である言葉は〔辞〕を見出し語につける。ついていない言葉は「詞」である。
はじめに、あらためてかな表記を掲げる。意味が分岐し、今日では漢字を書き分けているときは、その漢字表記を列記する。そのうえで、後に述べる[座標軸]を、ローマ字で表す。
◯において、構造語による内的定義ができる場合、これをおこなう。
他の基本的な詞と辞によってその詞を定義する。ことば相互の関係を明らかにし、それらの言葉によってその言葉を明確に位置づける。辞は、◯において、その言葉のはたらきを、他の基本的な詞と辞によって定義する。
日本語はいわゆる母音の転換で意味を発展させる。そこで必要に応じてローマ字表記も併せ、構造語の相互連関を述べる。
構造語をこえて意味を補足するときはそれを《》内に述べる。《》内のことは◆でくりかえされることもある。
※は補注を意味する。
他の詞との違いなどの考察。注意、備考、等の補注。またタミル語に由来をもつ言葉はそれを明記する。必要なところに随時置く。
現在のタミル語は独自の文字をもつ。それは紀元4〜5世紀に北インドで用いられたブラーフミー文字をその源とする。したがって、タミル語が日本列島に至った紀元前十世紀には文字はなかった。古代タミル語はローマ字にアクセント類を付加した方法で表記されることもある。本定義集では、タミル語起源を明示するときにそのローマ字表記を<>内に記すが、それはアクセント類、その他の記号を除いたものとする。したがって正確にタミル語を表すものではない。
上代特殊仮名遣いの母音の甲類と乙類の問題について。次の点を踏まえる。
古代において別の語であるとされていたことを確認する。同時に、後にこの区別がなくなったということは、一定の関連を古代においても認めていたことを意味する。よって、関連する別語、意味を区別しようとしてなされた使い分けであるとし、使い分けの意味を考える。
◆において根幹的な定義をおこなう。
必要ならば近代語も用いて、意味の定義に向かう。言葉を定義する根拠は人の経験である。近代語を含めた言葉で構造語を定義しようとすることは逆に近代造語もまた再定義することになる。ここにおいては、日本語世界の経験が根拠となる。それを述べる。
構造語においては、構造語の諸関係を明示することが、定義のはじまりである。そのうえで、定義する人の経験をもとに、根幹的な意味を定義する。この両面からの定義が、土台である。そしてこれは、つねに更新され展開され深められる。
言葉は定義を求める。定義は新たな世の経験を踏まえて更新される。定義と更新の永続運動、それが定義集である。
▲で、自動詞、他動詞などの区分を示す。
▼で、以上の定義を踏まえて、分化した言葉の意味を述べる。
他の言葉との違いもここで述べる。▽はさらに分化した諸々の意味である。
◇は用例である。古典からの用例、現代日本語の用例。
−【 】は派生語である。
四、[五十音図の座標軸]について
ことばには必要に応じてローマ字による表記をつける。ローマ字表記の意味を定めておく。
用いるのはいわゆる五十音図である。五十音図とは何か。五十音図は二つの座標軸をもっている。「あいうえお」の段と、「あかさたな…」の行である。日本語は、二つの座標軸でかな文字が決まる構造をもっている。それはそのようにとらえられた音の構造でもある。平安時代にこの事実が発見された。五十音図の発見には悉曇学が寄与した。発見された音の組織は日本語固有のものであった。語を分析するのに五十音図の座標を活用する。

それぞれの段と行を指示する記号として、アルファベットを借用する。a行のみは、段を指示する座標軸であるとともに、それ自身文字であるという二重の性格を持っている。a行は正しくは「ゼロ行」なのであるが、慣用にしたがって「a行」とする。われわれの立場は、西洋語の音素による日本語の解析ではない。あくまで座標の記号として用いる。
これが基本である。たとえば「ち」音はt行i段にあり、座標は(t,i)である。座標表示を簡略して[ti]と書く。ただし、a行のみはゼロ行であったので、行表示はない。例えば「い」の座標は(,i)であり、簡略した表示は[i]とする。[ ]はそれが座標の指示であることを意味する。かな文字言葉はいくつかの座標で指示されたかなの連続である。
このように現在の日本語における座標を基本とする。そのうえで古代日本語が現在より多くの音をもっており、当時別の座標として認識されていた場合には、必要なときにそれを区別する。たとえば「はる(晴る)」は現代日本語では[haru]であるが、古代には[faru]であった。
ここで重要なことは、この簡略表示はあくまで日本語の構造から定まる座標表示であって外から持ち込まれた音素の分析ではない、ということである。そもそもわれわれは、音素、つまりこれ以上分解できない音の単位が、どの言葉にも適用できるような普遍的なものとして存在するかどうか問わない。
次に、副次的な音図がある。これは、濁音と拗音の系列である。これらは、「どんどん進む」や「にゃんにゃんと鳴く」のような擬声語および擬態語で古くから発達してきた。それが漢字の音読みに生かされ今日に至っている。
濁音:
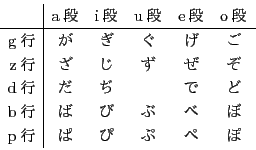
拗音:
もともと拗音とは中世悉曇学の用語で、カ・サ・タ・ナ・ハ・マ・ヤ・ラ・ワなどの音のことをいった。現代日本語では、ア・ヤ・ワ行以外の各行清濁音のすべてにあって、行座標が指示する音と段座標が指示する音の間にa行の[i]とy段が挟まれたうえで詰めて[i]を落として発音されると考えられているヤ行拗音と、k行とg行でw段が挟まれると考えられているワ行拗音がある。
母音「あ」にはさらに「や」と「わ」があるとすることで、拗音を別扱いしないこともできるが、それは今後の研究課題とする。
「きゃ」は[ka]に[iy]が挟まり詰められたもので座標は(ky,a)である。これは[kya]のように指示する。ア・ヤ・ワ行以外の各行をx行とすれば、ヤ行に対応して「xya」、「xyu」、「xyo」のすべてがある。
昔はたとえば f行が区別されていた。今日はh行にまとまっているが、例えば「端」は[fa]であった。今日では「言う」は[iu]であるが、かつては[ifu]であった。また「神」も「上」もいまは[kami]であるが、万葉集の時代には二つの[i]は区別されていた。これは万葉仮名の研究から明らかになったが、このように語源を考えるときには、かつてあった段や行を掘り起こさなければならない。これを明示するときは、←で示す。